|
|
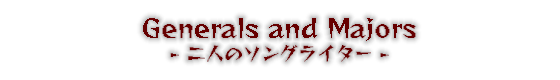 |
|
XTC の魅力の一つに、異なるタイプの優れたソングライターの存在が挙げられます。
一人は言わずと知れた中心人物 Andy Partridge。そして、もう一人はベーシストの Colin Moulding。他の追従を許さぬほど個性的で曲者的(?)な楽曲を量産する鬼才と、キャッチー且つ伝統的な英国ポップのソング・ライティングの継承者を両輪とすることで、他のポスト・パンク・バンドにはない独特の味わいを長年醸し出し続けているのです。 (米国のバンドに例えると、The Cars の Ric Ocasek と Benjamin Orr の関係に近いでしょうか。バンドの個性を代表するリーダーと、メロディアスなヒットソングを書けるベーシストのコンビというような) |
|
|
XTC を唯一無二の存在としているのは Andy の作品であり、逆に言えばXTCのコアなファンのほとんどは
Andy の曲に参ってしまった経験を持つはずでしょう。Andy 自身「俺の歌がバンドのキャラクターの75%だ」とも明言しているそうです。
Andy の作風を特徴付けるものとしてしばしば挙げられるのは、アヴァンギャルドでフリーキーな音楽とポップなメロディーの融合です。Andy は若い頃から Sun Ra などのフリー・ジャズや Captain Beefheart などのアヴァンギャルド・テイストのアート・ロックを吸収していたそうです。その一方で Jimi Hendrix、Led Zeppelin、Taste などのハード・ロック、New York Dolls や Stoogies などグラムがかった元祖パンク、そしてもちろん Beatles や Kinks といった英国ポップの影響を受けています。このような雑多な音楽的素養が混ぜこぜになって、Andy 独自のポップ世界を培って来た訳です。要は取っ付き易いメロディーの中に隠し味的にアヴァンギャルドなセンスが挿入されているのです。これが「毒」「ひねり」「屈折感」という言葉で表される要素となり、XTC を形容する上によく使用されるターム、「ひねくれポップ」を形成していった訳です。 この「ひねくれポップ」センスを最も象徴する楽曲が初期 XTC の代表曲「This Is Pop」でしょう。イントロからAメロにかけて、如何にも頭で作った風なへんてこりんなメロディー。良く言えば先鋭的でカッコ良い、悪く言えば取っ付きにくい印象の導入部から始まるので、初めて聞く人は「いったいどこが Pop なんだ?」と思うでしょう。それがサビに入ると突然人懐っこいメロディーに変貌して、"♪This is POP! Yeah! Yeah!"と歌われてしまいます。初期のナンバーの多くはこうしたパターンであり、私も最初に「変わっているけど面白い人達」という印象を受けました。 アヴァンギャルドな要素があってもきちんとポップスとして成立しているのが彼の作品の良いところでもあり、プログレッシヴ・ロックのような大作になったり、Captain Beefheart や Henry Cow、Can ほどアヴァンギャルドでもないので、誰にでも安心してお勧めできるものです。(おっと、Beefheart 達が誰にもお勧めできないと申しているのではありません^^;;。) 一方で、ポップと前衛性を両立させているミュージシャンと言えば 10CC (Godley & Creme) や Todd Rundgren が代表選手でありますが、彼らほどはポップス寄りでもない。あるいは Roy Wood や Bill Nelson よりは攻撃的でしょう。一番世界が近いのは初期の Brian Eno 辺りでしょうか。「Beatown」を聞いていると Eno の「Third Uncle」を連想します。まあ、主観的にはこんな位置付けですね。(余計わからないか) Andy について強調しなくてはならないのは、歌詞がまた素晴らしいこと。この人はダブル・ミーニングを多様するなど、英国人らしく相当レトリックに凝った作品を多く残しています。またメッセージ・ソングよりはパーソナルな視点からのステートメントというのがこの人の持ち味のようですね(これは Colin にも共通)。 いくつかは"私の好きな曲など"のコーナーで取り上げてますが、上げられなかった曲にも、コミュニケーションの不在を嘆く「No Lungage In Our Lungs」、82年頃の Andy の心中を偲ばせる「Senses Working Overtime」、ショウビズ批判の「Funk Pop a Roll」、世捨て人っぽさ丸出しの「Desert Island」、軍事競争時代を憂う「This World Over」、上昇志向の世界を離れ自己の人間性の回復を促す「Chalkhills And Children」、そして後世への期待と浄化の願いを感じさせる「The Last Balloon」などは、歌詞が良いので歌詞カードを読みながら聞く事をお勧めします。 そして Andy のもう一つの特徴として、アルバムに一曲はヘビーな作品があることです。「Complicated Game」、「Travels in Nihilon」、「Train Running Low on Soul Coal」などアルバムの最後を飾る曲に多いですね。これも Andy の作風や性格を考える上で重要な鍵となることでしょう。 |
 |
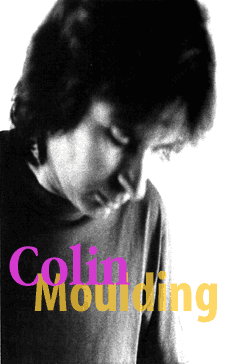 |
方や Colin はポップなポテンシャルを持った素直な曲が多く、アルバムに2、3曲と少ないが必ず存在する彼の作品をこよなく愛するファンも居ます。かく言う私もその一人。彼の曲だけを集めたテープをよく作ったりしました。Andy
に比べると世に出た作品数は少ないですが、トータルでは CD3枚分に相当する容量はあります。
ただ、素直と言いましてもそれは Andy と比較しての話。彼の作品は職人的で相当高度です。これは Andy のソングライティングを彼なりに消化吸収した結果得た手法ゆえと思っています。初期の2枚までの彼の作品は明らかにAndyの作風を踏襲していました。そしてColinが独自性を発揮し始めるのは初のシングル・ヒットとなった「Life Begins At the Hop」、更に初めて XTC のアコースティック曲となる「Ten Feet Tall」を作った1979年からと思われます。そしてこれを含む『Drums And Wires』と「Making Plans for Nigel」の商業的成功から、彼の曲もまた XTC にとって必要不可欠となっていきました。 彼の作風が独特なのはベーシストであることと関係あるかも知れません。初期の作品を聞くと、彼らの演奏の中で彼のベースが相当エッセンシャルな要素であることがわかります。XTC はダブヴァージョンのリミックス作品をいくつか作り上げていますが、どれも真っ先に耳につくのがあの独特なベースの音です。そしてそれはリズム・キープの要素に留まらず、常にギターやキーボードとは全然別のフレーズを奏でるメロディー楽器として位置付けられます。Andy によれば Colin は一曲のベース・ラインを作るのに物凄く時間を掛けるのだそうです。また『Skylarking』収録時にベース・ラインの事で揉めたことがきっかけで、Colin が XTC を離脱する寸前まで行ったことも伝えられています。 フレットレス・ベースを駆使して縦横無尽に駆け巡る彼のベースですが、奏法は明らかに Paul McCartney の影響だろうと思われます(またレゲエの要素もあります)。一方で彼はルート音を外したベース・ラインを作るのが得意です。Brian Wilson の様ですね。Colin の書いた「Cinical Days」のベースを聞いてみて下さい。とんでもないでしょう。実際に彼の作品には Brian Wilson を連想させる曲もいくつか存在しており、この辺りも彼の作家性に反映しているのではないかなどと想像しています。 個人的には彼の作品はとても好きで、3rd 以降のほとんどのアルバムで真っ先に好きになるのは Colin の曲です。『Drums And Wires』では「Ten Feet Tall」、『Black Sea』では「Love At First Sight」、『English Settlement』では「English Roundabout」、『Mummer』では「In Loving Memory of a Name」、『The Big Express』では「I Remember The Sun」、『Skylarking』では「Big Day」、『Oranges And Lemons』では「Cinical Days」、『Nonsuch』では「Bungalow」。オリジナル・アルバム未収録曲にも「Blame The Weather」や「The Good Things」等の佳曲があります。 『Nonsuch』では Colin 作品が4曲含まれ、作風もバラエティに富んでいてますます幅を広げている印象がありましたが、最新作『Apple Venus Volume 1』は2曲のみで、その内容も Andy 作品の充実ぶりに比べるとちょっと地味な印象。最近はイージーリスニングに凝っているという彼ですが、ファンとしてはそうした志向も踏まえて、もっともっとメロディアスな作品を作って欲しいぞと願っています。 |
|
|
Copyright (c) circustown.net 1999 - 2000, All Right Reserved.
