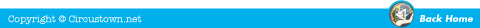| 2014.06.30 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
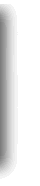
|
The Lonely Surfer
Jack Nitzsche The Lonely Surfer (1963) |
 | ||
ナイアガラ・レーベルのオモテの名盤が『A Long Vacation』だとすればウラの名盤ともいえるのが『Let’s Ondo Again』だろう。多羅尾伴内楽團名義の3枚目のアルバムとして出され、大滝詠一の諧謔趣味の究極をいったのがこのアルバムだった。Chubby Checkerの「Let’s Twist Again」を布谷文夫のヴォーカルをフィーチャーして音頭に仕立て上げた「Let’s Ondo Again」。この痛快無比な傑作を最後に、コロンビア・レコードをディストリビューターとする第1期のナイアガラはいったん幕を下ろした。この2年半後にCBSソニーをディストリビューターとして再開したナイアガラの第1弾が“ロンバケ”だったのだから、この落差にファンの多くは度肝を抜かれたのではないだろうか。かくいう僕は“ロンバケ”世代なので、81年当時すでにコロンビア時代の多羅尾伴内楽團シリーズは廃盤になっていて、ソニーで編集された『Niagara Fall Stars』でその片鱗を聴くことができるだけだった。ナイアガラ読本“All About Niagara”に出ているジャケット写真を見ながら音を想像するしかない時間が長く続いたと思う。この来る日も来る日も本を熟読しながら悶々と音を想像するという日々は今から思うとなかなか濃密な日々だったと思う。
さて、その多羅尾伴内楽團シリーズは駒沢裕城のスチール・ギターをフィーチャーした“哀愁のヨーロッパ・サウンド”『多羅尾伴内楽團Vol.1』、Vol.2が村松邦男のエレキ・ギターをフィーチャーした“サーフィン・サウンド”と続いた。どちらも古今東西の名曲をカヴァーしたインスト作品集である。
多羅尾伴内とは大滝詠一のアレンジャー名であり、ナイアガラがPhil Spectorのフィレス・レコードのようなレーベルを目指していたことから、多羅尾伴内とはすなわちフィレスでのJack Nitzsche。同様にプロデューサー大瀧詠一はPhil Spector、エンジニア笛吹銅次はLarry Levinと変名によってその役割を明確に分けていた。本来はフィレスのようにそれぞれを担う人材が必要だったのだろうが、すべてを一人でこなさなければいけなかったところがナイアガラ・レコードの苦しいところだったと思う。
アレンジャーとしてのもう一つの顔を強調したインスト・アルバム『多羅尾伴内楽團』。作品のコンセプトはJack Nitzscheの『The Lonely Surfer』というインスト・アルバムをベースにしており、Vol.1のジャケットはこのアルバムのパロディにもなっている。件の“All About Niagara”のVol.1の紹介ページにはこの『The Lonely Surfer』のジャケット写真が添えられており、当時多羅尾伴内楽團さえ聴けていなかった僕は、このアルバムはいったいどんなアルバムなんだろうとさらに悶々としたものだ。多羅尾伴内楽團はその数年後に『Niagara Black Vox』で聴くことができたが、Jack Nitzscheのこのアルバムはさらに20年近くたってCDで出るまで聴いたことがなかった。

フィレスでの活動の合間にいわゆる“レッキング・クルー”の面々とのセッションで制作されたこのアルバム。自らの作品のほかに「Ebb Tide」や「世界残酷物語のテーマ」、「荒野の七人のテーマ」などスタンダードや映画音楽も取り上げているのだが、そのどれもがエッジの効いたアレンジ。ベースをリード楽器として際立たせる非常に個性的なアレンジが施されている。イージー・リスニングとしてはとても跳ねた印象で、のちの『Niagara Song Book』の雰囲気にもどことなく通じていくものがあるような気がする。
自作の「Puerto Vallarta」はJackie DeShannonに書いた「Needles And Pins」のアレンジそのままで、ストリングスが印象的でとてもドラマティックな美しい曲。この感じを無理やりこじつけるなら『多羅尾伴内楽團Vol.1』で「ゆきやこんこん」が「君は天然色」につながったような感じと同じだろうか。
Jack Nitzscheは実に様々な仕事をした人で、Phil Spectorとの仕事以降、The Rolling StonesやBuffalo Springfield、Neil Youngなどロック・フィールドでの活動をはじめ、『エクソシスト』や『愛と青春の旅立ち』など数多くの映画音楽も手掛けた。曲を聴くとゾクゾクとする作曲家たちは何人もいるが、Jack Nitzscheからはアレンジで突破していく緊張感にそれらと同種の雰囲気を感じることができる。
多才で器用な印象の人だが、大滝さんはフィレスの関係者の中でもとりわけこの器用な才人、Jack Nitzscheにもっとも大きなシンパシーを感じていたのではないかという気がする。
今日の1曲
Tweet