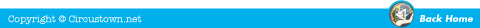| 2014.03.21 - 追悼大瀧詠一 | ||

|
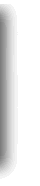
|
1969年のドラッグレース
大滝詠一 EACH TIME (1984) |
 | ||
日記をつける習慣はないのだけれども30年前の今日、1984年3月21日に何をしていたのかは日付が語る事実として忘れるはずのない日である。この日が発売日の『EACH TIME』を買いに街で一番大きなレコード店に出掛けて行ったからである。もっとも3.21を忘れるはずはないのだけれども・・・。
たしか店の入り口近くの目立つところにジャケットの絵を大きく引き伸ばしたポスターがディスプレイされていた。広い店内では店中にジャケットを模したポスターが天井から下がっていて、お店全体がこのアルバムの発売を祝福しているかのようだった。当時は九州の地方都市のレコード店にまで強力なプロモーションが行き届くほどレコードが売れていたのだ。”ロンバケ”のヒットに続けと鼻息の荒いレコード会社の意気込みも多分にあったのだと思う。
でもこの日のことはそんなレコード店の様子をぼんやりと覚えているだけで、帰って初めて針を落とした時のことは覚えていない。肝心なことはいつも欠落していて周辺のどうでもいいことばかり覚えているのは今も昔も変わらない気がする。
30年前の自分は、まさか30年後の同じ日に同じ行動をしているなどとは思いもよらなかった。今日30年目の『EACH TIME』の発売。そしてその同じ日にまさかその人に花を手向けることになるとは・・・。でもこうした巡り合わせというのを常々因果として喜ぶのが大瀧さんという人だったような気がする。
今回はこの”30th Anniversary Edition”を初めてプレーヤーにかけた印象を書いておこうと思う。ヘッドフォンじゃなくてまずスピーカーで聴いたのだけれども、前回の20th盤と比較しても一聴してはっきり分かるほど音が豊かになっている。音がふくよかでエネルギーがナチュラルに立ち上がってきている感じ。デジタルなエッジをあんまり感じない。それは二度目にヘッドフォンで聴くとさらにはっきりと分かる。僕の耳でもそれと分かるほど大瀧さんが丹念にリマスターを施したことが分かる作りになっている。
それにしてもこのアルバムは出るたびに曲順が変わる。初出のアナログ盤(28AH1555)は「魔法の瞳」から始まり「レイクサイド ストーリー」で終わる全9曲。この2年後の86年に出たアナログの『Complete EACH TIME』(28AH2001)は「Bachelor Girl」と「フィヨルドの少女」が加わって「夏のペーパーバック」から始まり「フィヨルド〜」で終わる全11曲の構成。初めてCD化された(35DH78)はオリジナル9曲の構成。89年のリマスターCD(27DH5303)では「魔法の瞳」と「ガラス壜の中の船」が「Bachelor Girl」と「フィヨルド〜」に差し替わり、曲順も「1969年のドラッグレース」から始まり「レイクサイド〜」で終わる9曲。CD選書シリーズの(CSCL1664)では再びオリジナルの構成に戻る。CD化された『Complete〜』(32DH555)はアナログの『Complete〜』と同じ。20thリマスター盤(SRCL5002)はボーナス・トラックを除くと『Complete〜』と同じ曲数だが「魔法の瞳」が3曲目から9曲目に移動している。そして今回の30th盤(SRCL8005)は20th盤をベースに「恋のナックルボール」と「魔法の瞳」が入れ替わっている。
最初の印象が強いのでどうしてもオリジナルの曲順のほうがすんなりと入ってきていたのだけど、これだけ曲順が変わるとそれも気にならなくなってくる。
アナログ盤が出た直後、『EACH TIME SINGLE VOX』としてアルバムに収めている曲をすべて12インチのシングルで限定盤としてリリースしたことがあるので、大瀧さんとしては楽曲単位として捉えているところがあったのではないかとも思う。”ロンバケ”はあれしかないという曲順なのだけれども『EACH TIME』にはどんな順番で聴かせるのが一番いいのか長い試行錯誤があったのではないか。あるいはリマスターを施すたびに楽曲の表情が変わってきて順番が変わったのかもしれない。
このアルバムは”ロンバケ”よりもさらに切ないアルバムである。それは結果としてこの84年のアルバムがオリジナル・アルバムとしては最後のアルバムになったということだけではない。松本隆−大瀧詠一というはっぴいえんどから続いてきたコンビの、曲と詞、歌と詞が放つロマンティシズムの苦さや憂いを内包しているからだという気がしなくもないからだ。でも松本さんは大瀧さんとのコラボレーションはこのアルバムで一区切りにしようと思っていたと言う。はっぴいえんど時代に細野さんと大瀧さんと3人でドライブ旅行をした時のことをモチーフにして書いたという「1969年のドラッグレース」にはそうした思いが籠められているのだと。大瀧さんがこれ以降まとまった作品を発表しなくなった理由にはことによるとそうしたこともあるのかもしれない。はっぴいえんど時代のエピソードを書いた曲がひとつのピリオドとなるべき曲だったということも、今聴くと何か不思議な符牒を感じずにはいられない。
そういうことが詞や曲に微妙に作用しているからかこのアルバムはいつも物悲しく響く。
「銀色のジェット」や「ガラス壜の中の船」のような別れの曲が多いこともある。若い頃はそんなペシミスティックな曲に心を揺さぶられてメランコリックな気分になったりもした。でも、今はそれ以上にこのアルバムの辿ってきた巡り合わせのようなものに想いが至る。
”Final Complete”というのが試行錯誤を繰り返してきたこのアルバムの到達点を意味しているのか、それとも大瀧さん自身が手掛けるNiagara最後の作品ということを暗示しているのか。重層的で複合的で物事には必然の帰結がある。凡そ意味のないことはないのだよと大瀧さんに言われているような気がする。
最後の最後に『EACH TIME』の究極の姿を残して大瀧さんは旅だった。鮮やかでふくよかでとても悲しいこの作品をだから僕たちはこれからもずっと抱きしめていく。
Tweet